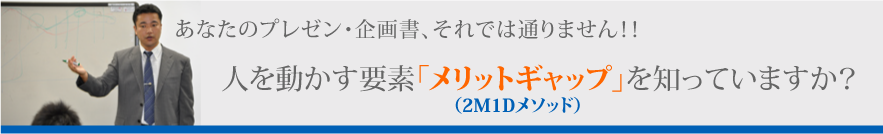プレゼンテーションのコツは聞き手の集中力管理!!
メリットギャップのお話をする前に、あなたに質問です。
1・・「A作業」をすると、あなたは「B権利」がもらえます。
どうでしょうか? あなたにとって、1は「A作業」をする切っ掛けになりますか。もちろん、作業労度であったり、権利の内容によって異なると思いますが、ここでは難しい話は抜きにして、直感的に考えてください。
では次に進みます。
2・・「A作業」をすると、あなたは「B権利」がもらえます。
「A作業」をしないと、あなたは「B権利」を失います。
今度は2つの内容を比べて同時に考えて見てください。
どうですか? 何となくですが、「失う」と言われてしまうと、「やっておこうかな」って気持ちになる人が多いのではないでしょうか。
それでは、最後です。
3・・「A作業」をすると、あなたは「B権利」が永久にもらえます。
「A作業」をしないと、あなたは「B権利」を永久に失います。
これも2つの内容を同時に考えてくださいさい。
さあ、どうでしょうか? 永久って言われてしまうとかなり「A作業」へのモチベーションが高くなったのではないでしょうか。
受け止めるニュアンスの程度の差はありますが、第3項まで全て、「A作業」をすると、あなたは「B権利」がもらえます。とした内容の文が記述されています。でも、なぜか第3項になるにつれて、作業をやったほうが良い様な感覚が芽生えませんでしたか。
極めて単純化した例ですが、これが「メリットギャップ」です。
第1項は、一応メリットらしい内容ですが、なんだか良くある客引きのように思えます。さすがに、これだけでは動き出す切っ掛けにはなり難いですね。
しかし、第2項ではどうでしょう。単に「作業しなければ、もらえません」とした内容の文を、下に加えただけです。要するに、もらえるメリットだけでなく、失うデメリットも記載されています。
この時点で動くかどうかについては、個人差があると思います。しかし、少なくとも第1項よりは、なにかコツンと来た感じです。
そして、第3項です。今度は内容は同じですが「永久」と記載されています。第2項と比べて、かなり強い切っ掛けになってませんか。
では、第2項と第3項では、何が異なるのでしょうか。それは、メリットとデメリットの差、つまりメリットギャップが体感的に拡大しているからなのです。当然、第1項はメリットだけの記載なので、メリットギャップは体感されません。
この差が、大きければ大きいほど、受け止める側の印象は強くなります。
これが、メリットギャップが重要とされる所以です。
こうしたメリットギャップを適切に用いて、聞き手と対話しつつ結論へと導くのが、成功するプレゼンテーション、採用される企画書・提案書の王道です。
もちろん、その他のメリットや価値も理解してもらうことが前提ですので、それらへも配慮が必要です。商品やサービスの説明を丁寧に行い、その有用性もプレゼン資料や企画書に落とし込めたとしても、それだけでは人は動かないのです。
このメリットギャップを、どのように考え作為し準備段階で資料に落とし込み、どのタイミングでストーリーに反映し、どんな見せ方で企画書当に記述するのかのノウハウが「2M1Dメソッド」です。
メリットギャップを導く「2M1Dメソッド」はプレゼンテーションだけでなく、企画書や提案書類など、全てに通用する方法です。
そもそも、プレゼンも企画書等も、聞き手(相手)を動かすことが目的なのですから、ノウハウが異なるはずがないのです。
一人でも多くの方が、当研究所のセミナーや教材により、メリットギャップをご理解し、2M1Dメソッドを活用して活躍の場を広げて行けることを願ってやみません。
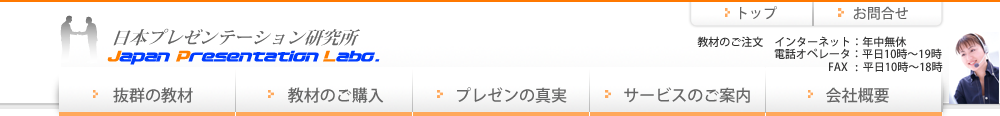

日本プレゼンテーション研究所 > メリットギャップとは